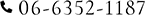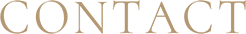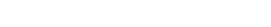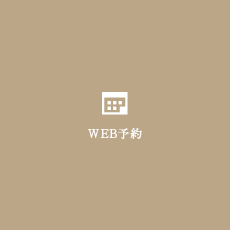医院ブログ一覧 Blog List
むし歯は揺れ動くプロセス
歯のエナメル質表面は、唾液の海の中でちょうど潮の満ち引きのようにミネラルが出たり入ったり揺れ動きながら、ある一定の状態を維持しているのです。 カリオロジー(むし歯学)では、むし歯は動的な平衡(バランス)の過程であると定義されます。 ひとことで言えば、いつも揺れながら安定している状態のバランスが崩れた時にむし歯になるのです。 歯のエナメル質表面の少し下のミネ …
メンテナンスがなぜ必要か(2) 増田歯科・矯正歯科
(2)ブラッシングのチェック・指導正しいブラッシング法の指導を受けた直後はそのとおりに磨けていても、時間が経つにつれて以前の癖が出て、磨き残しが増えてしまうことも少なくありません定期的に磨き方をチェックし、必要に応じてブラッシングを再度指導します
メンテナンスがなぜ必要か(1) 増田歯科・矯正歯科
(1)再発の早期発見歯周病菌をゼロにするのは難しく、プラークがたまってくれば容易に再発します重症化を防ぐために、定期的な観察で再発をいち早く発見し、治療につなげることが大切です
「メインテナンス(定期検診)」 増田歯科・矯正歯科
歯周病の症状が改善したら治療は一段落ですが、それで終わりではありません歯周病は再発しやすい病気なので、口の中をずっといい状態に維持していくための「メンテナンス(定期検診)」を一生続ける必要がありますどのくらいの頻度でメンテナンスするかは、口の中の状態や全身状態などによって変わります
歯はいつも動いている 増田歯科・矯正歯科
歯列はいつも後ろから前へ押されています特に乳歯から永久歯に生え変わる時は一番奥にある第二大臼歯や親知らずが生えようとして、前へ前へと前列の歯を押しています歯が移動することによって歯列の土台である歯茎の形も変わってきますこうなると当然噛み合うべき上下の歯の法則はくずれ、噛み合わせにズレが生じてしまうのですそして、噛み合う相手の歯がなくなった場合は、その歯が飛び出し …
親知らずで不正咬合や体調不良‼増田歯科・矯正歯科
親知らずは、三番目の大臼歯で、歯列の一番奥にある歯のことです先天的に生えない人もいますが、だいたいの人は大人になってから生えてきます親知らずは、生えるスペースが足りないため、歯ぐきに埋もれた状態でも、生える途中でも、他の歯を前へ前へと押していきますそのため、特に前歯が重なりやすく、その分、歯列が小さくなってしまいますこうなると噛み合わせが深くなっていき、顎が後方 …
正常な舌の発達をさせるには 増田歯科・矯正歯科
正常な舌の発達をさせるためには何が必要でしょうか?それは、舌の筋肉を作る助けになるような行為を積極的にやらせることです乳児期であれば、ゴムのかたいおしゃぶりを吸わせ、指しゃぶりを積極的にやらせることです哺乳瓶の乳首もかたいものが好ましいです。まず、「吸う、吸う、吸う」という運動で舌の先のほうの筋肉が作られますその行為によって出た唾液を、「飲む、飲む、飲む」という …
不正咬合の原因は?? 増田歯科・矯正歯科
歯並びや噛み合わせの土台となる顎は、成長過程のいつ、どこで、正常になったり異常になったりすると思いますか?それは舌の筋肉の発育と関係すると言われていますそれも特に、出生から10歳くらいまでの間ですこれはちょうど歯が生えてくる前から、永久歯に生え変わるまでくらいの時期にあたりますつまり、生まれてから順調に舌の筋肉の発達が進まないと顎の発達も弱く、未熟な顎には歯の生 …
将来、顎に問題が生じる幼児の反対咬合 増田歯科・矯正歯科
成長期に上の歯列より下の歯が2本以上外側に出ている場合は、下の顎の過剰な発育や上の顎の成長不足成長停止につながりそのままにしておくと問題が生じてきますたとえば加齢とともに「顎変形症」などによる可能性が大であり、成長・発育が終わり、成人を迎えるころになって治療しようとしても、顎の骨の変形については矯正だけでは治らないので、外科で顎の骨を切り、矯正治療によって咬合の …
バイオフィルㇺ~繁殖する歯の細菌~
定期的なクリーニングの目的はむし歯や歯周病の原因となるバイオフィルムの破壊と除去です 歯の表面は新陳代謝がないため、殺菌剤でも退治できない細菌のかたまりができてしまいます この細菌のかたまりがバイオフィルムです 歯科では歯の表面についたバイオフィルムをデンタルプラーク=歯垢と呼んでいます